「無印良品」として知られる良品計画は、シンプルで高品質な商品を提供し続けるブランドとして、日本国内外で多くの支持を集めています。その良品計画を率いるのが、2021年に社長に就任した清水智(しみず さとし)氏です。
近年、小売業界はデジタル化の波にさらされる一方で、消費者とのリアルな接点も重要視されています。清水氏が推進する経営戦略は、デジタル技術の活用と地域密着型の店舗運営を融合させるというもの。この方針は、良品計画の今後の成長を大きく左右すると言われています。
本記事では、清水智氏が掲げるデジタル戦略と地域密着型経営の融合について詳しく解説し、良品計画の未来について考察します。
清水智氏のプロフィール
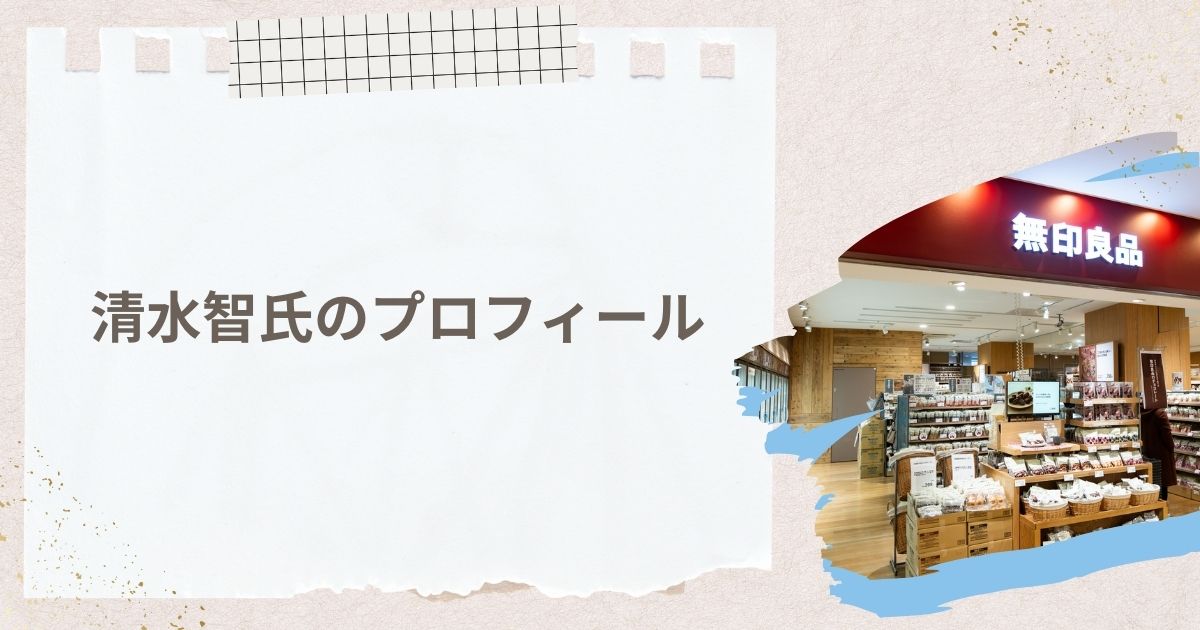
まずは、良品計画社長・清水智氏のプロフィールについて見ていきましょう。

画像:良品計画公式サイト
| 名前 | 清水 智(しみず さとし) |
|---|---|
| 生年月日 | 1974年3月14日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身大学 | 日本大学農獣医学部(現生物資源科学部) |
| 職業 | 良品計画代表取締役社長 |
良品計画の舵取りを担う清水智氏は、1974年3月14日生まれの51歳で、東京都出身です。日本大学農獣医学部(現生物資源科学部)を卒業後、1996年に良品計画に新卒で入社しました。彼が初めて「無印良品」の店長として店舗運営を任されたのは東京都中央区にある「無印良品銀座一丁目店」でした。
その後商品開発部門へ異動し、ディストリビューターやマーチャンダイザー、デザイン担当といった商品開発に関する実務経験などを経験。生活雑貨部のファニチャー担当だった際には、多くの人から愛用され大ヒットした「壁に付けられる家具」を開発しました。
そして、2011年から無印良品有楽町店の店長として再び店舗への勤務に戻ります。2015年に取締役販売部長に就任。
その後も着々とキャリアを磨き、2022年には副社長就任。そして、2024年11月23日付で代表取締役社長に就任しました。
清水智氏が描くデジタル戦略:顧客体験の深化と業務効率化
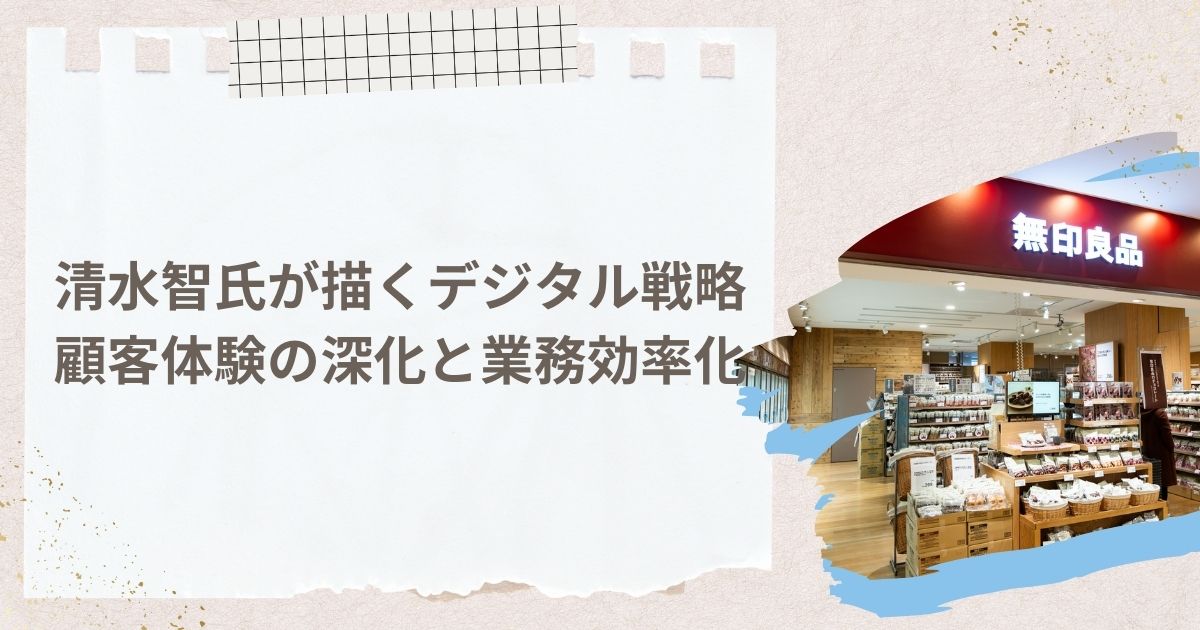
良品計画では、「顧客の声を商品開発に活かす」という取り組みが創業当時から大切にされてきました。2013年からサービス開始されたスマートフォンアプリ「MUJI passport」を継続的に利用している人も多いのではないでしょうか。
実は、良品計画はデジタルマーケティングにいち早く取り組んできた企業のひとつ。しかし、2010年頃、リアルの店舗とネットショップが対立してしまうという課題を抱えていました。それを解決するツールのひとつとなっているのが「MUJI passport」です。
「MUJI passport」では、「MUJIマイル」という独自のポイントサービスがあり、店舗やネットで買い物をした時はもちろん、顧客が店舗にチェックインした際や無印良品に対して意見を投稿した際にもマイルが貯まります。
ちなみに、ネットストアで注文した商品を店舗で受け取ることができる「店舗受け取りサービス」も充実しています。また、一部の店舗での取り扱いサービスにはなりますが、ネットストアで注文した商品を店舗に併設される専用ロッカーで受け取れるシステムを導入しているところもあります。
清水智氏の「顧客を大切にする」という方針
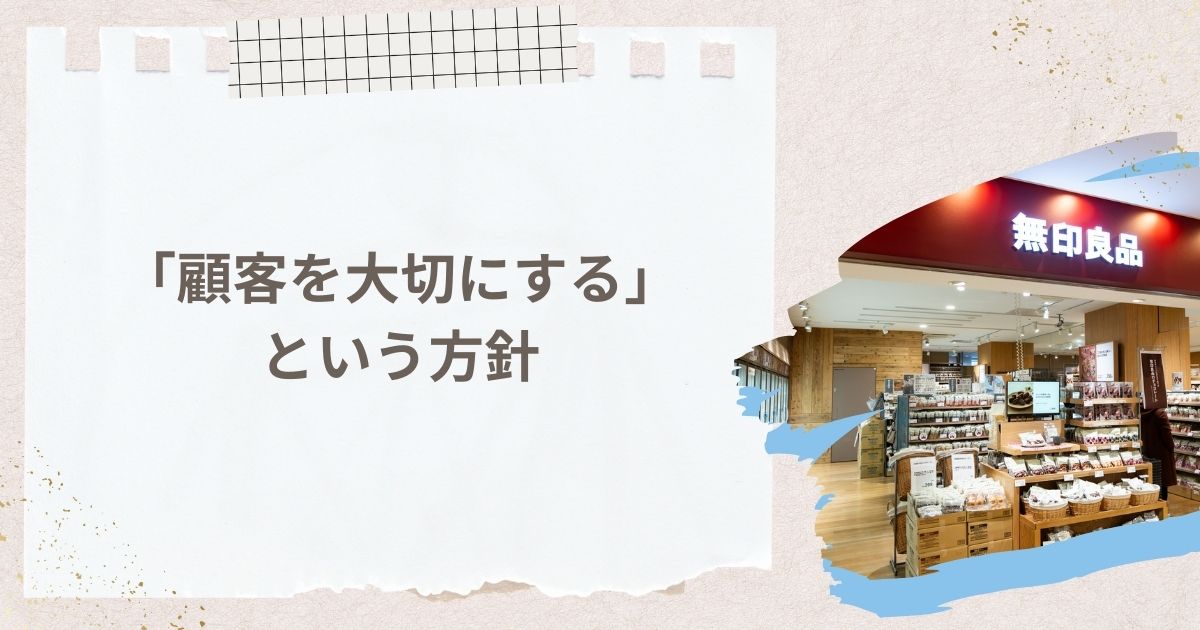
元より、良品計画では「顧客を大切にする」という文化が大事に継承されてきましたが、清水智氏もその想いを強く受け継いでいる経営者のひとりと言えます。
その想いを強くしたのは、やはり店舗での販売経験である、とも過去のインタビューで答えていたことがあります。清水智氏が店長を務めていた「無印良品 有楽町」は2018年12月に多くの人に惜しまれながら閉店しましたが、当時の有楽町の店舗は世界旗艦店という位置付けの、良品計画にとって大事な店舗でした。(※現在、世界旗艦店の位置付けは「無印良品 銀座」へ受け継がれています)
彼は店長として販売のトップに立っていた頃から、「顧客」を大事にするために、現場で顧客に向き合う「従業員」が気持ちよく働ける環境づくりの大切さも重要視していました。社長となった現在でも、この考え方は彼の根幹として在り続けています。
清水智氏は、MUJI REPORT 2024(経営方針)の社長メッセージの中で、このような言葉を残しています。
「良品計画の夢」は、個々の従業員が大切な人と大切なことを共有し、互いをいたわることのできるゆとりや時間を確保でき、日々プライドとわくわく感に満ちあふれた環境で仕事ができる状態を整えることです。良品計画の従業員は、自社の商品やブランドが好きで、自然が好きで、人間関係を尊重する人が大勢います。報酬と休暇の充実を図れば、家族や友人、自然環境や地域を大切にすることにお金と時間が使われ、良品計画が目指す「感じ良い暮らしと社会」の実現につながると考えます。
引用:MUJI REPORT 2024(2024年8月期)
現場や現実での経験によって、自分で見た顧客や従業員の姿を想い浮かべ、今後も無印良品を多くの人々から愛されるブランドにしていくことでしょう。
清水智氏が前社長から受け継いだもの
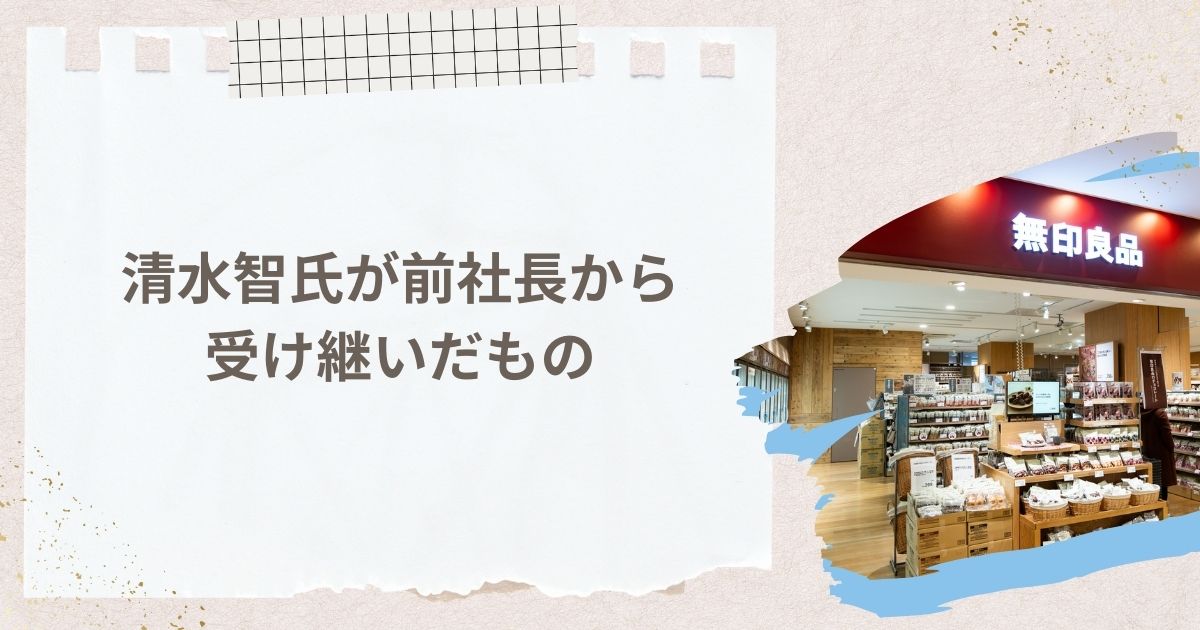
さて、良品計画の前社長(現会長)である堂前氏は、クリエイティブな発想を持つ人物として知られています。2021年からを「第二創業期」と位置付けた堂前氏は、その広い知見を活かし、良品計画(無印良品)を未来へ続く企業にするための戦略を考え、進めてきました。
清水智氏へ社長が交代されたのは2024年11月のことですが、清水智氏の持ち味は「実行力」。つまり、彼に託されたのは前社長が組み立てた戦略をできるだけ早く「実行」に移し、同じように早く成果を出すことです。
彼が打ち出した新たな経営方針では、2027年8月期までに、国内・海外ともに年60店の店舗展開と純増を加速させるというもの。今でも業績は好調に推移しているところですが、今後は営業収益、営業利益を年平均10%以上も伸ばすという方針です。
「無印良品」といえば、現状日本国内でも「ムジラー」と呼ばれるようなファンが多くいますが、それをさらに世界にまで拡大するというのが、今後良品計画の目指していくところなのでしょう。
無印良品・清水智社長が目指すもう一つの指針「地域密着型経営」とは
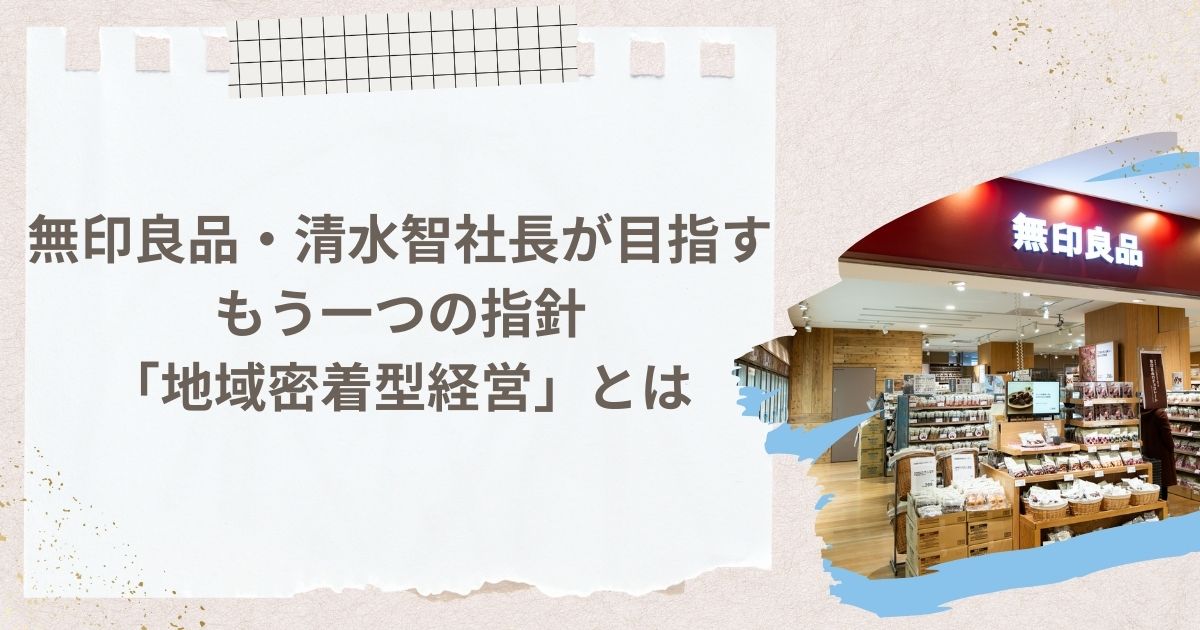
良品計画では、全国に展開する店舗を「コミュニティセンター」として捉えています。それぞれの店舗を中心にして地域資源が循環できるような仕組みを広げることで、地域資源を活用した産業の発展や現地の経済の活性化などを目指しています。
とくに、地域事業部のひとつとして位置付けられている千葉事業部では、千葉ならではの地域循環システムの構築を進めています。以下は、千葉事業部の行う活動の一例です。
里のMUJI みんなみの里

引用:無印良品公式サイト
千葉県鴨川市にある「里のMUJI みんなみの里」は、無印良品とCafé&Meal MUJI、それから農産物や物産品の販売所などが併設された総合交流ターミナルです。地域の人たちが日常で集ったり、鴨川を訪れる人たちが気軽に立ち寄ったりできる場所を目指して建てられました。
物産品を買うだけではなく、いちご狩りやみかん狩りなどといった農業体験の提供や、地域の情報発信なども行っており、観光目的で来た人々にも鴨川の良さや生産者とのつながりを意識してもらえる場所として知られています。もちろん、Café&Meal MUJIでも鴨川産の長狭米を使ったメニューなど地域ならではのメニューを楽しめます。
2024年4月には、千葉県の地域材を活用し、周辺の自然が一望できる「里山デッキ」を新設。地域の人々(小さな子供がいるファミリーやペット連れの方なども)がお弁当などを持って気軽に利用できるのはもちろん、Café&Meal MUJIでテイクアウトメニューを購入するのもおすすめです。
鴨川里山トラスト

引用:良品計画公式サイト
鴨川里山トラストは、2014年から「無印良品くらしの良品研究所」と「NPO法人うず」が共同で行ってきた里山文化の継承活動です。
千葉県内の無印良品の店舗を窓口にし、顧客とともに田植え(有機米の会)や大豆の種まき(手作り味噌の会・手作り醤油の会・自然酒の会)などといった業里山文化体験を行うことを続けています。
これらの活動には、高齢化にともない維持管理が難しくなっている里山空間の保全を進める目的を達成するだけではなく、人と自然が調和する美しい景色を次世代へと引き継いでいきたいという想いも込められています。
まとめ
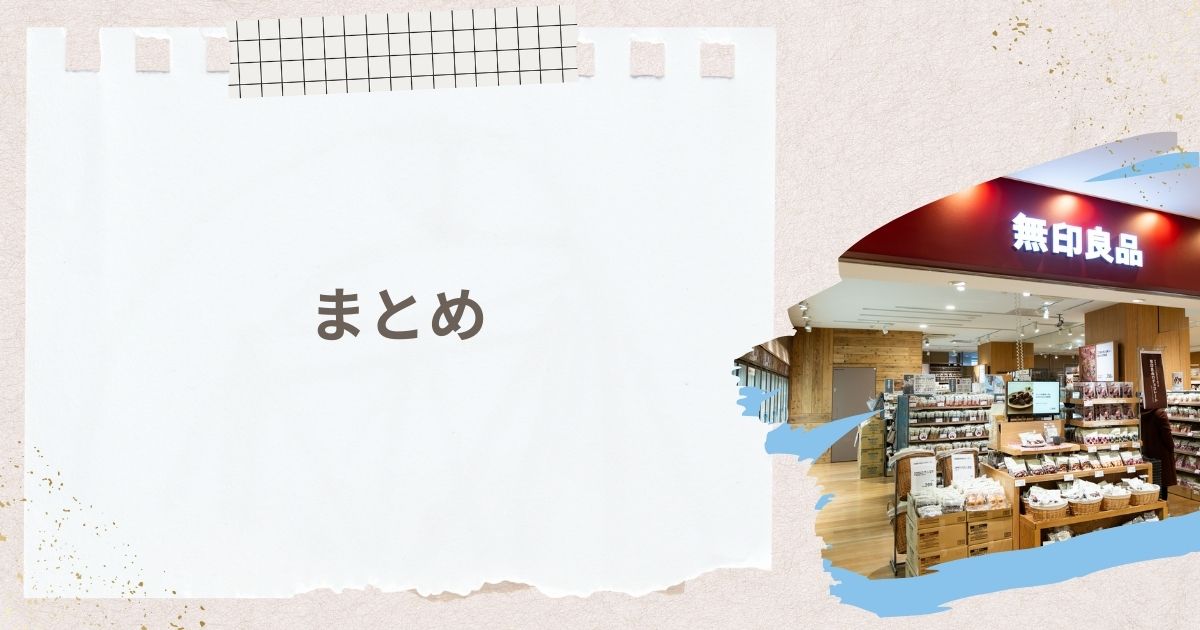
清水智氏が率いる良品計画は、デジタル戦略と地域密着型経営を融合させることで、新たな成長を目指しています。MUJI passportを活用したデジタル施策による顧客体験の向上や、地域資源を生かした持続可能な店舗運営は、これからの小売業のモデルケースとなっていくのかもしれません。
また、清水氏の「顧客を大切にする」という理念は、単なる販売戦略にとどまらず、従業員の働きやすい環境づくりにも反映されています。このような姿勢がブランドへの信頼を生み、無印良品が国内外で愛され続ける理由のひとつとなっています。
今後、良品計画はデジタルとリアルをシームレスに融合させながら、より地域に根ざした展開を加速させていくでしょう。その成長戦略がどのような成果を生むのか、引き続き注目が集まります。
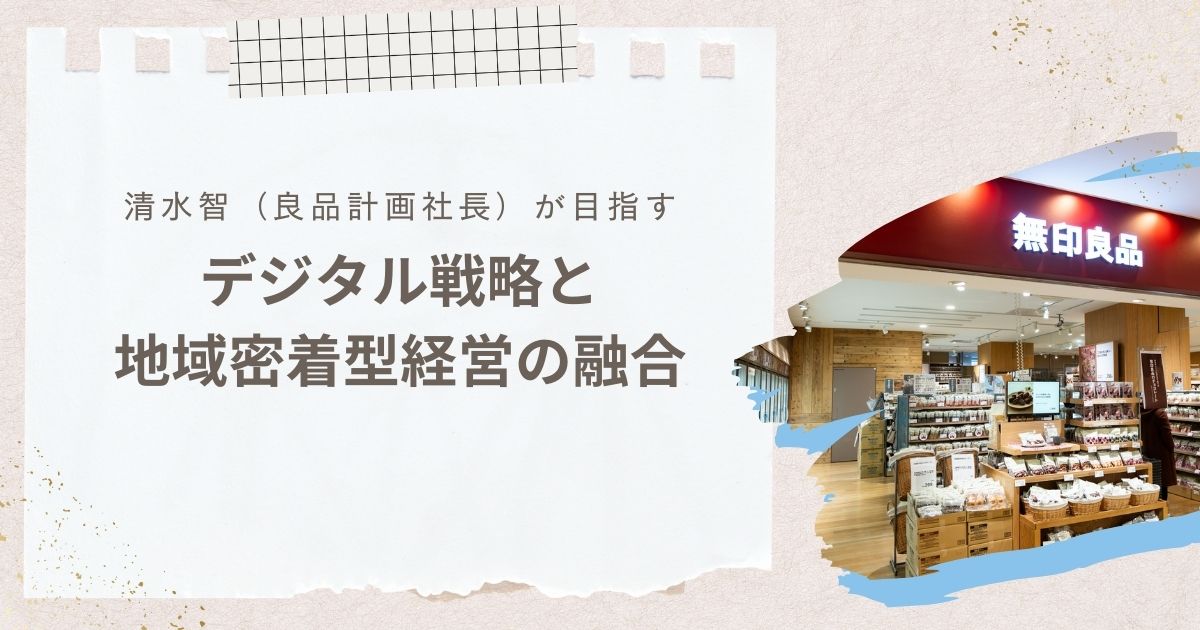
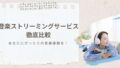
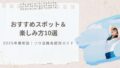
コメント